法務の三類型とは??
三類型によって理解が進む?
前回、企業法務のためにはビジネスへの理解が不可欠であるという話とともに、決して企業法務が特殊な業務ではないという話をしました。
ただ、これで分かったことは、「特殊ではない」というだけで、企業法務が何を指すかということの答についてはなにも回答していません。
そこで今回は、法務の三類型と呼ばれる概念を用いて、企業法務について理解していこうと思います。
法務の三類型は、企業法務というものを理解するうえで、非常に有用な概念です。
臨床法務・予防法務・戦略法務
その、企業法務を理解するうえで有用な三類型とは、臨床法務・予防法務・戦略法務です。
臨床法務とは、具体的な事案に即した法解釈や法的戦略を決定することを言います。
実際に訴えられたり、逆に訴えるケースのほか、いわゆる契約書のリーガルチェックもこれに該当します。
日本の歴史から見ると、これが一番古い類型です。
もともと、多くの企業で「総務部文書課」といったセクションから成り立つ企業法務は、もともと契約書それ自体を書面として管理することを目的としていました。
その中で契約書間の整合性チェックや、それ自体のリスクも管理するようになり、このような業務をしていくことになりました。
新しい≠重要な仕事
一方で、予防法務や戦略法務という領域は、具体的なリスクに対応することを目的としたものではありません。
例えば、契約書のリスクを低減するための営業への勉強会や、ひな形整理が予防法務に分類されると考えられていますが、これは、まだ見ぬリスクを未然に防止することを目的としています。
さらに戦略法務は抽象的で、自分たちにとって有利なように経営を進めるために法務の知識を活かそうという業務です。
一時期、「臨床から予防、予防から戦略へ」といったことが盛んに言われ、より抽象度の高い業務の推進が行われたことがありますが、決して、予防や戦略だから重要な仕事ではないということは、かなり重要なポイントです。
具体的な事案に対する対応力がつくから、抽象度の高い状態でも予防ができ、抽象度の高い状態での予防が活きてくるから、具体的な事案での対応ができる、という関係性を無視しては、企業法務はできません。
それぞれの三類型を、その時々の状況に合わせてうまく使い分けることが重要です。
三類型からわかること
このように、現在ではあらぬ誤解を生んでしまうことから、あまり使われなくなった企業法務の三類型ですが、この三類型は非常に示唆に富んでいます。
まず、企業法務は具体的な事案に対する対応から抽象度の高い経営に関する事項まで非常にグラデーションがあるということです。
契約書対応や法令対応、時には法律を変えること(例えばロビイング)さえ、企業法務の業務に含まれることになります。
また、時には商品それ自体の勉強会も含めて、業務内容に応じた多様な知識を求められるということも、重要なポイントです。
「法務とビジネス、両方の知識を活かして、会社の企業活動をより円滑にする」という、非常に幅広い領域が企業法務に含まれるということです。
決して暗い部屋に閉じこもって契約書を読んでいるだけの仕事ではないということです。
次回からは、三類型に代わって用いられる二つの概念に着目し、企業法務の意味合いをさらに掘り下げます。
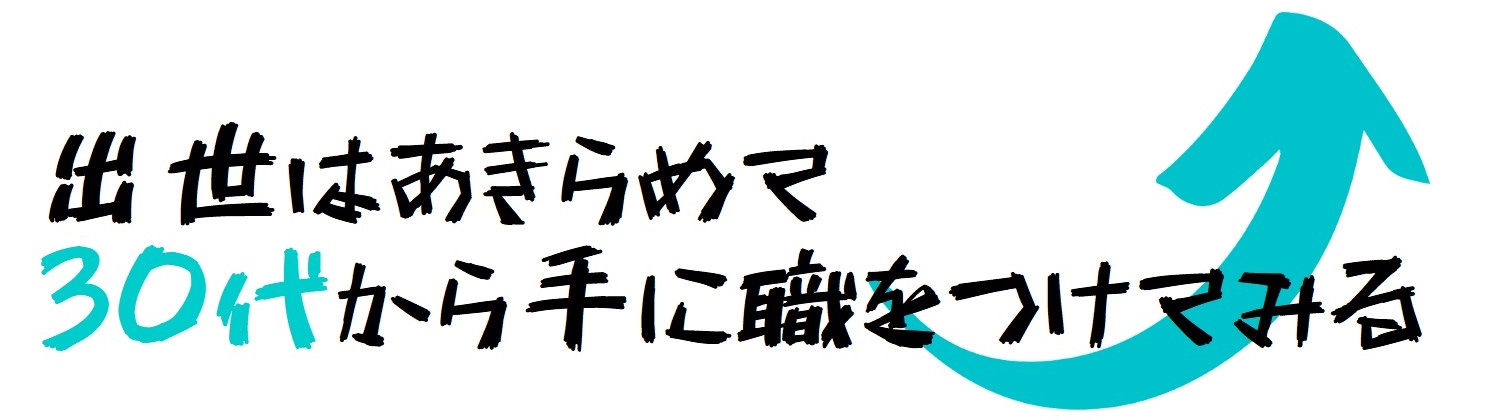



コメント