意気込み
さて、先週、毎週一回くらいはブログ更新をしっかりしていきたいという話をしましたが、早速シリーズものの記事を書くと、ネタに困らなくて済むので、新しく企業法務について考えていきたいと思います。
僕自身、法科大学院出身で、周囲の同窓の多くは現在弁護士や検察官として職務に全うしています。
そんな中で、企業法務の仕事をしていると、「法科大学院出身者だから特別その仕事ができるんだ」と思われることが多いです。
ただ、多くの場合、そのイメージは大きな乖離があり、かなり間違っています。
このシリーズでは、そういった誤解を解消しつつ、一流の企業法務部員になるための方法について考えていきたいと思います。
企業法務=特別な仕事は誤解か?
法律学は特別なものか?
僕の周囲には、企業法務は特別な仕事であり、弁護士資格を保有するかそれに準ずる経験を持った人だけができる仕事であるというイメージを持った人が多いです。
その理由は様々ですが、法科大学院制度・新司法試験制度ができて15年以上が経過し、「法律は6年間学ぶ、医学と同じもの」というイメージが定着したことが原因の一つだと言われています。
一般的なビジネスマン・ビジネスウーマンにとって、法律学はアンタッチャブルなものというイメージがついてしまっています。
ただ、多くの人が日々買い物をし、スマホの通信料を支払い、就職の際に雇用契約を締結します。
この間にも、法律は当然に適用されます。
法律学は決して特別なものではなく、本来は身近なものであるべきです。
弁護士にはできない仕事?
むしろ、僕の考えでは、企業法務の仕事は弁護士資格を保有しているだけの人にはできません。
というのも、企業法務の仕事の大半は、ビジネスへの理解だからです。
企業法務というと、一日中契約書とにらめっこをしたり、何か法律を盾に後ろ向きなことを言う仕事だと思われがちですが、実際には、ビジネスをしっかり理解し、前向きに物事を進めるための仕事が非常に多いです。
単に契約書の中に記載されたリスクを洗い出すだけであれば、確かに弁護士でも可能ですが、「折り合いをつける」といったことをするためには、ビジネスへの理解が不可欠です。
イメージは審判と選手
野球の細かなルールを正確に頭に入れなくても野球ができるように、法律の細かな知識がなくても法務部員は務まります。
企業法務の仕事は、野球における選手の仕事に近いです。
野球のルールについて細かな知識を持つ審判よりも選手の方がいいプレイができるように、法律の知識を持つ弁護士よりもいいプレイができる法務部員は多数います。
良いプレイをする周囲の人を助け、自信も良いプレイをする、そんな企業法務の実態を、次回以降解説していきたいと思います!!
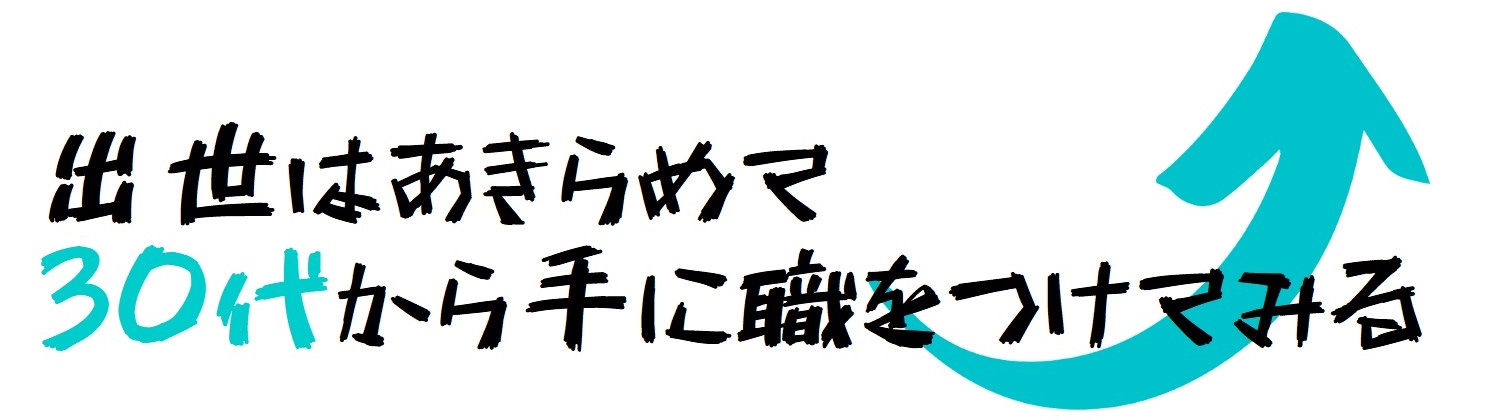



コメント